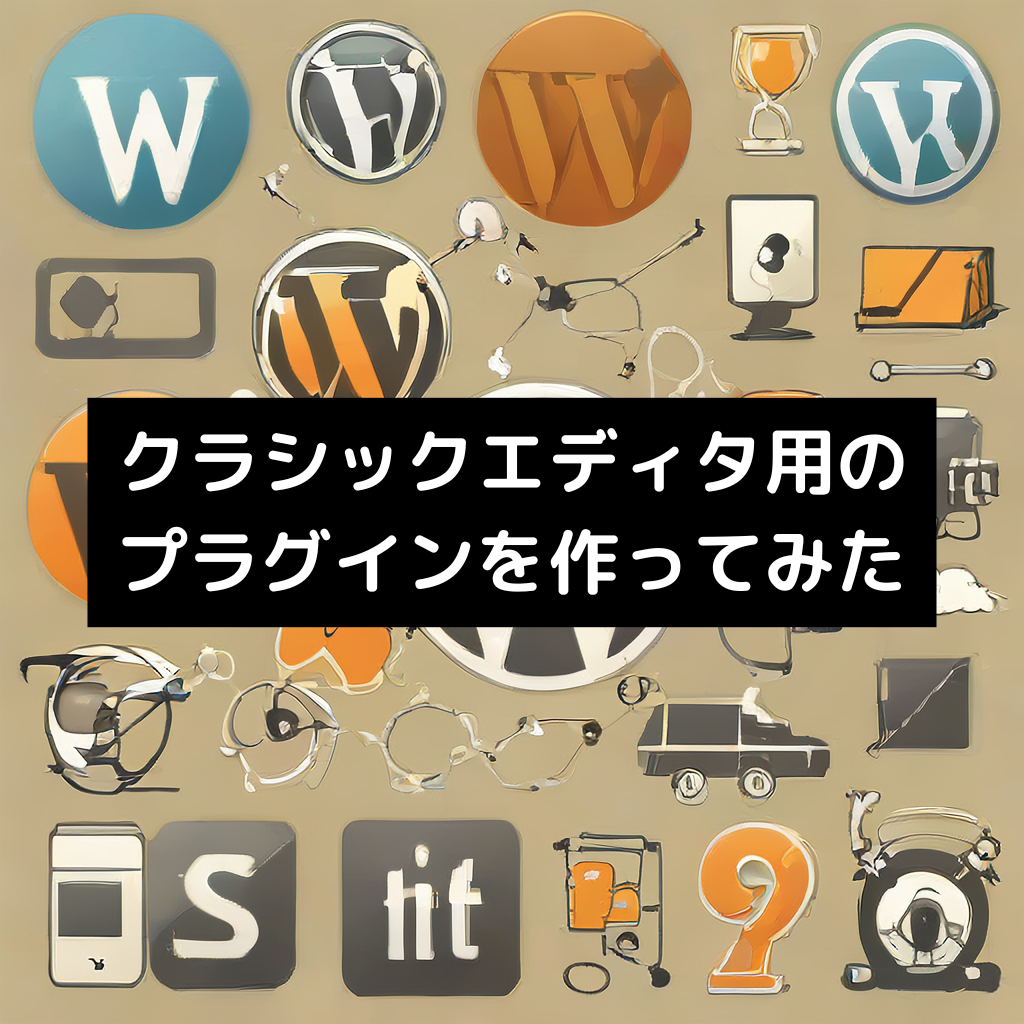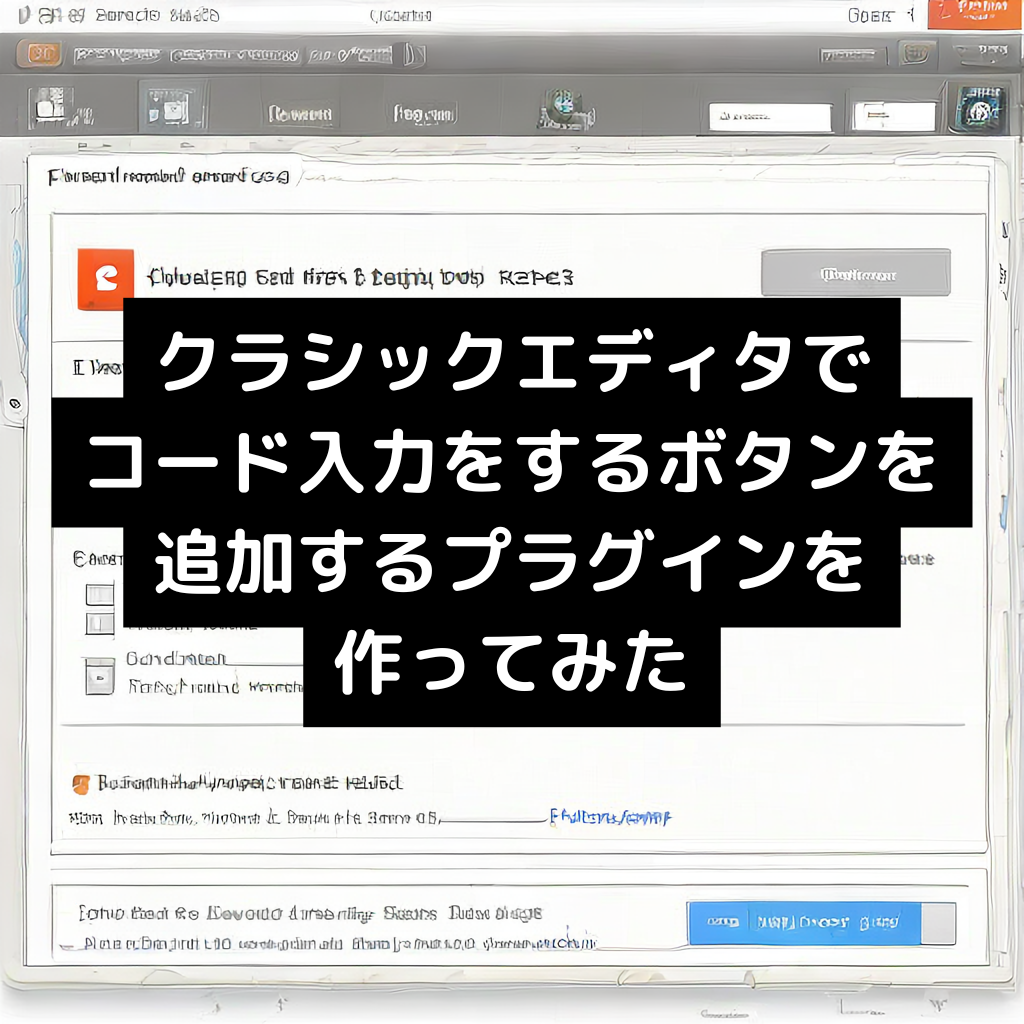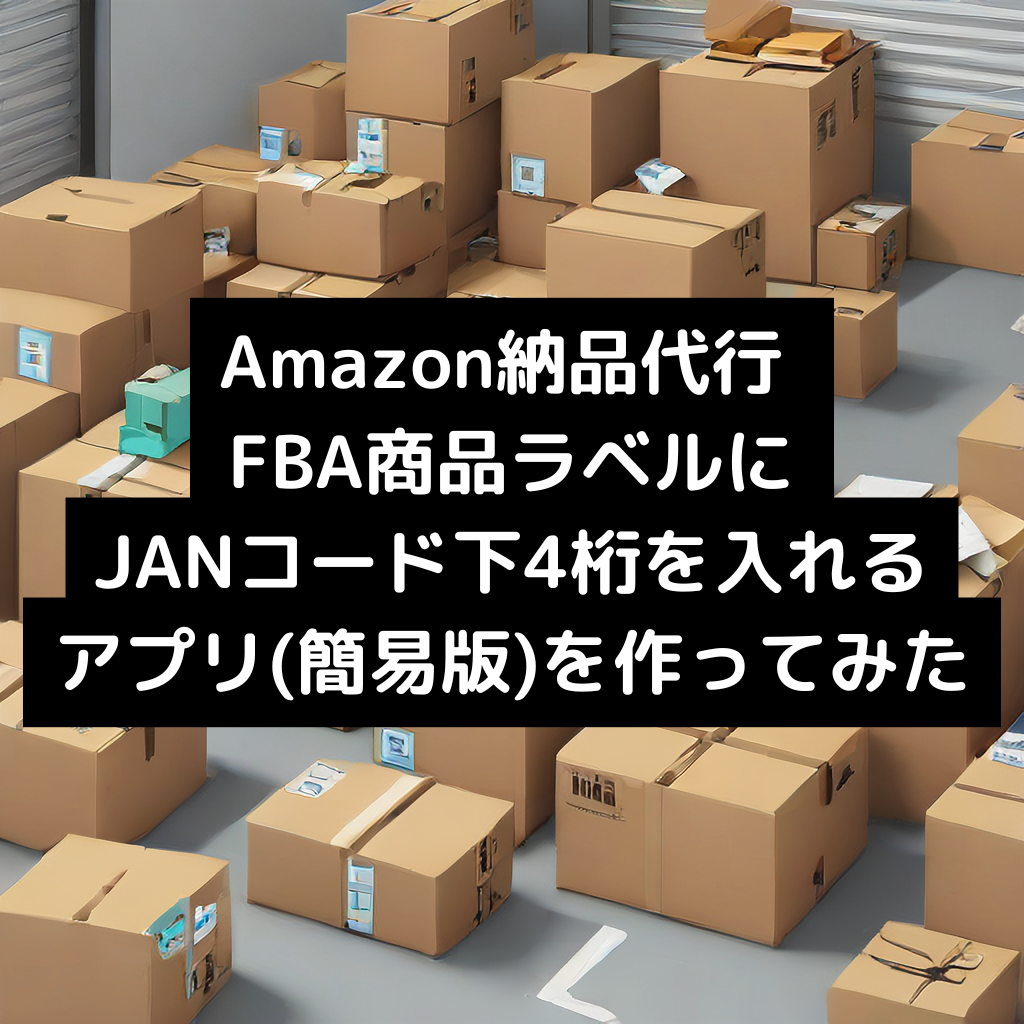chatGPTに記事を書いてもらってます
プログラムでは、「たくさんのデータをまとめて使いたい」場面がよくあります。 そんなときに便利なのが 配列(はいれつ) です!
配列ってなに?
配列とは、複数の値をひとつの変数でまとめて扱える箱のようなものです。
たとえば:
<?php $fruits = ["りんご", "バナナ", "みかん"]; ?>
$fruits という変数の中に「3つの果物」が入っています。
このようにカンマで区切って値を並べたものが配列です。
配列の中身を取り出すには?
<?php echo $fruits[0]; // りんご echo $fruits[1]; // バナナ echo $fruits[2]; // みかん ?>
ポイントは 数字(インデックス)で指定する こと!
最初の値は 0番 から始まるので注意しましょう!
foreach文で配列をまとめて処理!
配列の中身を1つずつ使いたいときは、foreach が便利です。
<?php
foreach ($fruits as $fruit) {
echo $fruit . "<br>";
}
?>
これで「りんご」「バナナ」「みかん」が順番に表示されます。
配列に関するキーワードまとめ
| キーワード | 説明 |
|---|---|
| 配列 | 複数の値をまとめて管理できる変数 |
| [](角カッコ) | 配列を作るとき、中身を取り出すときに使う |
| foreach | 配列を1つずつ取り出して処理するループ |
補足:配列の中には文字でも数字でもOK!
<?php $numbers = [10, 20, 30]; $names = ["田中", "鈴木", "佐藤"]; ?>
いろんなデータを一度に扱えるので、ループと組み合わせると超便利!
まとめ
- 配列は「たくさんのデータ」を1つにまとめる箱!
- 最初の値は「0番」から始まる
- foreach 文でまとめて処理できる!
キーで管理する「連想配列」
普通の配列は「0番」「1番」と番号(インデックス)で管理していましたが、
自分で名前(キー)をつけて管理する方法もあります。
それが 連想配列(れんそうはいれつ) です!
例:人の情報を連想配列でまとめる
<?php $person = [ "name" => "田中", "age" => 25, "job" => "エンジニア" ]; ?>
これは $person の中に「名前」「年齢」「職業」が入っている配列です。
数字じゃなくて「name」や「age」などの**キー(名前)**でアクセスできます。
中身を取り出すには?
<?php echo $person["name"]; // 田中 echo $person["age"]; // 25 echo $person["job"]; // エンジニア ?>
foreach で連想配列を扱う
<?php
foreach ($person as $key => $value) {
echo $key . " : " . $value . "<br>";
}
?>
name : 田中 みたいに、キーと値が順番に表示されます!
よく使う配列の関数たち
PHPでは、配列に対して便利な**関数(組み込みの命令)**がたくさんあります!
| 関数名 | 説明 | 例 | 結果 |
|---|---|---|---|
| count() | 配列の要素数を数える | count($fruits) | 3 |
| array_push() | 配列の最後に値を追加する | array_push($fruits, "ぶどう") | ["りんご", "バナナ", "みかん", "ぶどう"] |
| array_merge() | 複数の配列をまとめて一つにする | array_merge($a, $b) | 配列が合体する |
| in_array() | 値が配列の中にあるかをチェック | in_array("りんご", $fruits) | true/false |
関数に関しては次回以降学びます。関数というものがあるという認識だけでいいです
HTMLまとめ表(キーワード)
| キーワード | 説明 |
|---|---|
| 連想配列 | キーと値でデータを管理する配列 |
| foreach ($配列 as $キー => $値) | 連想配列を1つずつ取り出す書き方 |
| count() | 配列の中身の数を数える関数 |
| array_push() | 配列にデータを追加する関数 |
| in_array() | ある値が配列の中にあるか調べる |
まとめ
- 連想配列では数字ではなく「名前(キー)」で管理できる!
- foreach を使えば連想配列もラクに扱える!
- count() や array_push() などの配列関数もぜひ覚えておこう!
次回は、ユーザー入力に応じた処理などで使う「フォームとの連携」を学びましょう
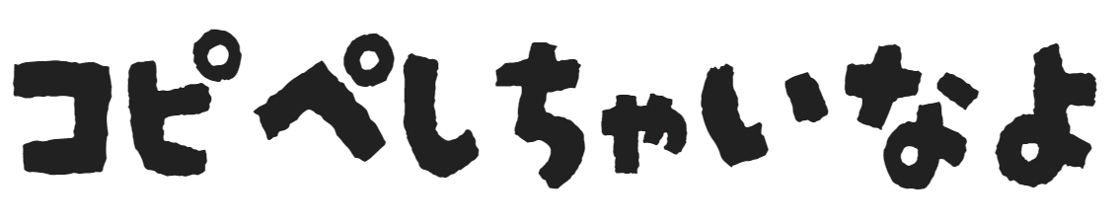

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/0fb3a2a7.a3eac612.0fb3a2a8.1146eb94/?me_id=1213310&item_id=21161259&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F8469%2F9784815618469_1_5.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)